法人でよくある未払いトラブルとは?債権回収の手順や代行業者、注意点などを解説!
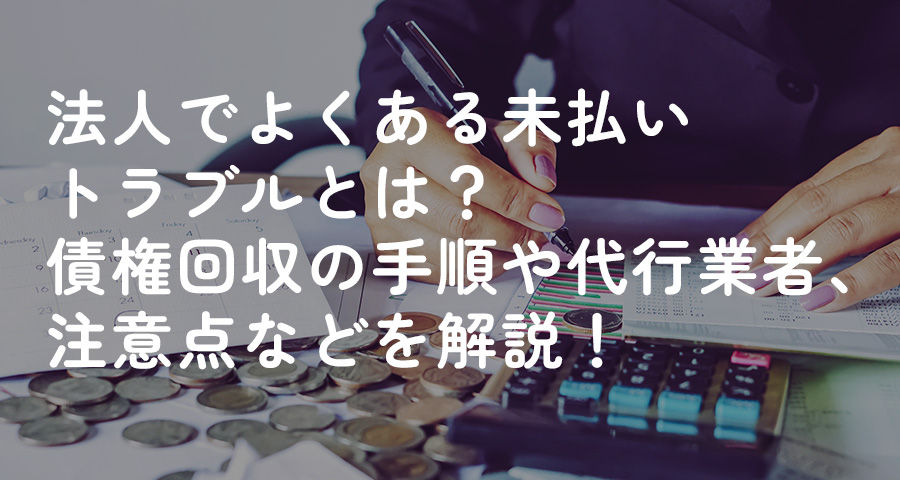
法人の債権は金額が数百万、1000万円を超えるようなケースが多く、未払いが起こることで大きなダメージを被ります。どのようなケースで法人の未払いが発生しがちなのか、万が一未払いが発生した場合に法人に対してどのように債権回収を行ったら良いのか解説します。
よくある法人の未払いトラブル
法人の未払いは、取引先の企業の経営状態に対する赤信号です。そのまま放置していると回収がどんどん困難になるので早期の対応を行う必要があります。どのようなトラブルがあるのか紹介します。
資金繰りの悪化による支払い遅延
経営状態が悪化すると資産が乏しくなり、毎月の収入をそのまま支払いに回すようになります。いわゆる自転車操業のような状況になり、何らかの事情で入金が遅れる、支払いの方が入金より大きくなると支払い遅延が発生するようになります。法人の取引において支払い遅延は信用に悪影響を及ぼし、会社によっては即取引停止になることが珍しくないため、基本的に支払い遅延だけはしないように気をつけるのが普通です。にもかかわらず支払い遅延が起こるということは、経営状態が相当のっぴきならない状況であることが推測されるため、倒産や事業閉鎖による債権回収不能のリスクが増大したと言えます。支払い遅延が発生した段階で、債務者の状況を把握し債権回収に向けて迅速に動く必要があります。支払いを猶予する場合は、現在の状況をヒアリングした上で明確な支払い期限を設定しましょう。
支払い遅延が常態化している
通常であれば支払い遅延が一度でもあれば、今後の取引を見合わせるケースは珍しくありません。しかし、元々の身内や知人、友人、長い付き合いの業者などであれば、取引をそのまま継続することがあるはずです。こういった場合、「最初は一月遅れで支払っていたのにそれすら滞るようになり未払い債権が半年分にまで膨らんでしまった」「支払い期日前後になると連絡が取りにくくなる」「入金が遅れているという言い訳を毎月してくる」といった現象が起こります。ここは支払いが遅れても大丈夫と後回しにされている可能性があり、最終的に倒産等で回収が不能になるリスクが大きくなるため、取引を停止し債権回収を行う覚悟が必要です。内容証明を発行するなど、法的な記録が残る方法で請求を行いましょう。
支払いの段になり難癖をつけ支払いを逃れようとする
納品後に連絡が取れず請求の段になって「納品物の品質が低い、依頼していたものと違う」と支払い拒否をしてくることがあります。さらに、「そんな契約をした覚えはない」と発注をしたこと自体を否定してくるケースも。契約書を作成せず口約束で仕事を受注すると起こりやすいトラブルです。口約束でも契約としての効力はありますが、こういったトラブルになった際に契約書がないと不利になります。担当者と仲が良くいつも口頭で契約して問題が発生していなかったが、担当者が退職し次の担当者からそんな契約のエビデンスが残っていないとして支払いを拒否されるということも耳にすることがあります。必ず契約書は作成し、納品物の仕様についても客観的に理解できるように記載をしましょう。
元々支払うつもりがない詐欺スキーム
支払い期日に支払いがなく、連絡も取れず、記載の住所に行ったらその客自体存在しなかったという詐欺スキームも存在します。法人であれば大丈夫だろうと審査なく取引するのは危険です。取引先のホームページ等を確認し、事業内容やテキストの文言に不審な点がないか、住所がバーチャルオフィスの物件でないか、資本金が低くないかなど、信用度をチェックした上で取引をすることが大切です。
倒産や事業閉鎖
期日に支払いがなく、実は倒産していたことが判明した、事業閉鎖でオフィスがもぬけの殻だったというトラブルも耳にします。支払い遅延が発生していたようなケースなら倒産を予測できるかもしれませんが、計画倒産で支払いを逃れようとする場合は見抜くことは難しいでしょう。しかし、倒産や事業閉鎖をしたからといって、債務者の支払い義務がなくなるとは限りません。弁護士に相談する等で全額ではないにしても債権回収をできる可能性は残っています。
また、会社が解散済みで資産もないと言い張るケースでも、代表者が別法人を立ち上げ同様の事業を行なっていたり、生活に不審な点があったりと、資産隠しが疑われる場合は、裁判を行うことで債権回収を目指すこととなります。
法人への債権回収の手順
法人への債権回収は大きく分けて3段階です。法的手段に出る前に督促の段階で回収できるのが理想ですが、法的手段に出る可能性も想定して、督促を行った旨のエビデンスを残しておきましょう。
①支払いがなければまずは督促
期日に支払いがなかった場合、まずは速やかに督促を行います。基本的には期日の16:00ごろまでに振り込みがなければ怪しいと考えた方が良いです。ただし、今はネットバンキングで24時間振り込みができるため、当日は督促を待った方が良いかもしれません。翌朝確認して振り込みがなければ、電話連絡と合わせてメール等エビデンスが残る形での連絡を行いましょう。初期対応を甘くすると、「ここは後回しして大丈夫」だと思われ回収まで時間がかかるリスクがあるため、しっかり督促を行う必要があります。その際に「いつまでに支払うか」「どのように支払うか(一括・分割等)」を明確にして、記録を残しておくようにしましょう。
②内容証明郵便の送付
上記で決めた期日に支払いがなく、さらに督促をしても明確な説明が得られない場合、内容証明郵便を送付します。記載内容としては最終の支払い期限、債権の内容、支払われなかった場合の措置についてです。内容証明郵便自体に法的強制力はありませんが、訴訟になった場合にしっかり請求を行ったという明確な証拠になり、さらに債務者にプレッシャーを与えることができます。
③裁判所による支払督促・裁判・強制執行
内容証明郵便を送っても事態の進展がなかった場合、法的手段に移ることになります。方法として手軽なのは「裁判所による支払督促」です。裁判よりも簡単で債務者の出廷が不要、さらに費用も数千円〜1万円前後で済むのは魅力です。特に債権額の上限もありません。ただし、債務者から異議申し立てがあった場合は裁判に移行するため、その場合は結果として印紙代・弁護士費用などがかかりますし、解決までの期間も長くなります。
債務者側に弁護士がついていたり、債権が1000万円を超えるような大きい場合は、初めから裁判で争うこともあります。
これらを実施し、最終的に強制執行となったとしても、債務者側に財産がなければ債権を回収できないとなるケースも珍しくありません。そのため、法的手段に頼る前の早い段階で債権を回収するアクションがやはり重要です。
法人への債権回収はどこが代行してくれるか
自力で債権回収が困難な場合、弁護士、司法書士、サービサーに依頼するという選択肢があります。それぞれに依頼できる内容と費用感を紹介します。
弁護士
弁護士に依頼すれば内容証明から督促状の作成、民事訴訟まで丸ごと依頼できます。債務者が支払い拒否の姿勢が明確であったり高額な債権である場合は、最初から法律の専門家である弁護士に依頼をするのが良いでしょう。
弁護士に依頼した場合、着手金が債権額の数%程度かかります。また債権を回収できた場合の成功報酬は回収額の10~20%程度が一般的です。
司法書士
司法書士は債権額が140万円以下の内容証明、支払督促、少額訴訟の場合に利用することができます。費用も1〜5万円程度であるため、少額債権の場合はまずは司法書士に相談するのがおすすめです。
サービサー
法務局から許可を受けた債権回収業者をサービサーといい、債権回収を依頼できる唯一の民間業者です。
主に2種類のサービス体系があり、「債権回収型」の場合は
・初期費用
・着手金
・成功報酬(回収額の30〜40%程度)
・交通費や内容証明郵便代などの実費
が発生します。
また、「債権買取型」の場合は
・額面の2〜3%で債権を買取
というのが一般的です。
2種類を比べた場合、明らかに債権買取型の方が回収額が少なくなります。ただし、回収額が激減しても良いから早期に現金化したい、自社ではもう回収できる見込みがない、訴訟を避けたい、複数の債権があるような場合は、損切りと考えて債権買取型を利用するのも仕方ありません。
法人への債権回収における注意点
法人への債権回収は督促方法や対応を誤ると自分が罪に問われるリスクがあります。やってはいけないことをしっかり押さえておきましょう。
脅迫や威圧的な行為はしない
支払いがないことでヒートアップし、暴言を吐いたり、大声で威圧したり、脅迫的な脅しをしてしまうケースがありますが、これは逆に「強要罪」や「名誉毀損罪」で訴えられてしまうリスクがあります。
営業時間外の訪問や電話はしない
営業時間外の訪問や電話、アポ無しの執拗な訪問は「業務妨害」や「不退去罪」に該当する可能性があります。電話での督促は繋がらない場合でも一日数回程度にとどめ、訪問する場合は極力アポを取るようにしましょう。それよりは文書等で記録をしっかり残しておくことが重要です。
根拠が曖昧な状態で請求・督促しない
契約書を作成していなかったケースで起こりがちですが、請求額や納品物の内容、そもそも契約があったかどうかを争っている状態で執拗に請求督促をすると、請求側が不法行為を行なっているとみなされることがあります。まずは、請求内容を確定させること、その前段階で争っている場合は債務者がむしろ下請法などの別件に抵触しているケースがあるので、弁護士に相談するのが良いでしょう。
自力で財産の取り立てを行わない
勝手に債務者の資産を差し押さえたり、商品や什器を持ち去るのは違法です。自力救済の禁止原則に反し、窃盗罪や器物損壊罪、占有離脱物横領罪、住居侵入罪などに問われます。
第三者に債権の情報を漏らさない
他人や他社に債務者が未払いであることを漏らしたり、債務者である企業に勤めている社員に「お宅の会社は未払いがある」と伝えることは名誉毀損やプライバシー侵害にあたります。特に最近はSNSにトラブルの内容を投稿することを目にしますが、これは名誉毀損に当たるリスクが非常に高く、債権を回収できるどころか逆に損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。
法人の未払いに対しては早めの対応が重要
自力での債権回収が困難な場合は、弁護士や司法書士、サービサーなどを利用することとなりますが、費用がかかりますし、そこまで一定の期間が経ってしまっているため満額回収自体も難しくなっていることが想定されます。期日に支払いがなかった時点で、速やかに督促対応を実施することで、早期の回収を実現しやすくなります。そのためには、地道なメールや電話、書面による支払いの依頼を続け、督促を継続していることのエビデンスを残すことが大切です。相手に心理的プレッシャーを与えることで支払われやすくなりますし、万が一法的対応に移行する場合も証拠が揃っている状態になります。
電話での督促業務を自動化する場合、オートコールを活用するという方法があります。ソフトプラン株式会社では格安・簡単なオートコールシステム「発助」を提供しています。

