個人顧客の未払いが発生しがちな業界とは。債権回収の手順や手段、未払いを防ぐ方法も解説。
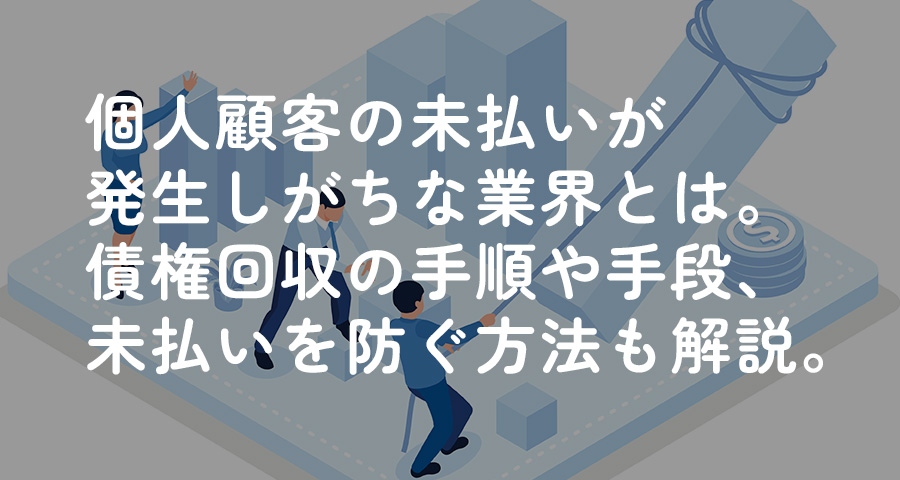
個人顧客の未払いが発生した場合に、債権回収はどのように行ったら良いのでしょうか。個人顧客の未払いは数千円から数万円と少額のものが大部分とはいえ、事業者としては確実に債権回収したいところです。未払いが発生しやすい業界や、債権回収の手順と手段、どうすれば未払いを防げるのかを解説します。
目次
個人顧客の未払いが多い業界7選
個人顧客への未払いが多いのはどのような業界なのでしょうか。7つ紹介します。
美容・健康業界
エステサロンやパーソナルジムなどの美容・健康業界は、回数券や年間コースの契約形態が多いです。数十万、百万円単位といった高額な料金のサービスが珍しくないため、回収不能のリスクは大きいです。初回無料や返金保証といったフレーズで集客をしているため、モラルの低い顧客が集まりやすかったり、経済力に不足のある10〜30代の顧客が中心であることも、回収不能の要因となっています。
教育・スクール系
月謝制が一般的な学習塾やカルチャースクールのような業種では、月末に支払われていないというトラブルが起きがちです。支払いなくそのまま音信不通になるケースもありますが、費用が数千円〜3万円程度なので泣き寝入りしてしまうケースも多く見られます。また、短期コースを受講してそのまま支払いなく逃げる、もしくは無料キャンセル期間が過ぎてからの一方的なキャンセルや当日現れず音信不通になるということも起こりがちです。
ブライダル・イベント業
ブライダルの際の支払いは大体3回に分けて行われます。予約金(内金)、中間金、最終支払いです。これは大抵の場合、結婚式を予約してから実際に行われるまで半年から1年程度かかることが多く、その間に状況が変わりキャンセルとなった場合にも費用を確実に回収するための仕組みです。多くの場合、式当日までに全部払い終わるような支払いサイトになっていますが、全体で3割程度後払いが可能な式場やブライダル会社も存在し、この場合は当然未払いのリスクが上がります。また、式当日に発生した料金は事後精算となるため、場合によっては「納得がいかない」「説明を受けていない」等のトラブルから回収が難航するケースもあります。
物販・通販・ネットショップ
多くの場合、決済機能付きのプラットフォームを利用しての取引になるため販売者への未払いは減ってきているジャンルではありますが、それでも個人顧客との直接取引での販売を行っている場合はトラブルがあります。代引き決済で受け取り拒否されると、商品は戻ってくるものの送料や手数料は店舗負担になり損失が出ます。また、請求書払いにしているケースも未払いのリスクがあります。新聞や牛乳配達などは後払いが一般的なため、未払いが起こりやすいです。
医療・福祉施設
病院では診察や治療、手術、入院後の支払いになるため、精算の段階で支払えないとなるケースがあります。また、老人ホーム等の福祉施設に入居しており、本人でなく親族が月額費用等を支払っている場合、経済状況の変化や資金が底をついた等で思わぬ未払いが発生することがあります。
士業・専門サービス
弁護士、司法書士、税理士等の士業も成功報酬型の案件に関しては、依頼者が成果に納得していないと支払わないとなるケースがあります。他にもカメラマンやSNS運用、マーケターなどの専門サービスも納品物や成果に納得がいかず請求面でトラブルになりがちです。
リフォーム
リフォームは料金は数十万から数百万円にもなり、回収不能のリスクが高い業種です。リフォームを行った結果に納得できない、こんな施工は頼んでいない、こんなに料金が発生するなんて聞いていないなど、工事完了後に未払いになることがあります。
よくある個人顧客の未払い・キャンセルトラブル
個人顧客の未払い・キャンセルトラブルは、決済プラットフォーム等を通さない直接取引をしている場合に起こりがちです。決済プラットフォームを通しての未払いだった場合は決済プラットフォーム側が債権者ですが、直接取引の場合は販売・サービス提供者側が債権者となり自身で督促をしなければなりません。
決済が不能なケースでよくあるのは
・サービスや商品提供後にクレジットカードで支払い不能だった
・請求書払いにしていたが期日までに振り込みがなかった
・無料キャンセル期間終了後にキャンセル、もしくは当日ドタキャンなどで、請求手段がない
これらの場合は、次の項に紹介する個人顧客への債権回収の手順を参考に、粘り強く対応する必要があります。
また、納得できないから払いたくないというケースもあります。この場合は、事前に契約書や利用規約、キャンセルポリシーに署名をもらっているか、顧客が説明を受けた証拠があるかどうかで交渉のしやすさが変わってきます。口頭のみでの契約だとトラブルの際に販売・サービス提供者側が不利になってしまいます。
個人顧客への債権回収の手順
個人顧客への債権回収は以下の手順で行います。
①支払い期限を過ぎたら、すぐにメールやSMS等でリマインドを行う(延滞1日〜1週間程度まで)。入金期限が過ぎている旨、振込金額を記載。
②リマインドで対応がない場合、電話で督促(延滞1週間〜3週間)。顧客の状況を聞き、いつまでに支払えるのか、支払い意思があるかを確認します。録音しておく等で必ず会話内容を記録しておきましょう。
③電話に出ない、もしくは電話で約束した支払い期日が守られない等の場合は、郵送による書面で督促します(延滞3週間〜2ヶ月)。書面には金額、本来の支払い期日、最終支払い期限、これまでの連絡履歴、支払われない場合は法的措置を取る可能性がある等を記載します。
④通常の郵送書面でも対応されない場合は内容証明郵便を送り、相手が対面で受領した記録を法的に残すのが最終手段です(延滞2ヶ月〜)。内容証明郵便を送っても反応がない場合は裁判に移行することになります。また、受取拒否をされた場合は、特定記録郵便で相手のポストに投函した履歴を残すことで裁判に移行します。
個人顧客への債権回収でやってはいけない対応
個人顧客への債権回収では
・深夜・早朝の電話・訪問(特定商取引法、迷惑防止条例違反)
・SNSでの晒し行為(名誉毀損、プライバシー侵害)
・嫌がらせ・威迫(恐喝罪、ストーカー防止法)
・繰り返しの自宅訪問(住居侵入、付きまとい行為)
は絶対に行わないようにしましょう。自分が加害者として法に触れてしまう可能性があります。
個人顧客への債権回収に使える法的手段とは
内容証明による督促でも効果がなかった場合、以下のような方法で法的に債権回収を行うことができます。ただし、仮に裁判で勝訴した場合にも相手が自発的に支払うとは限りませんし、さらに強制執行(差し押さえ)を行っても資産がなければ債権回収できないことがあります。債権の金額等で法的手段に出るか、できれば避けたいですが損切りと考えて回収を諦めるかを総合的に判断する必要があります。
少額訴訟
60万円以下の債権の場合、少額訴訟が最も手軽です。簡易裁判所による審理で1回で終了します。弁護士に依頼する場合は数万円かかりますが、自力で行うのであれば数千円の印紙代だけで可能です。判決後にも支払われない場合、裁判所が強制執行を行います。
通常訴訟
60万円以上の債権は通常訴訟になります。この場合は素人が自力で行うのは無理で、弁護士が必要になるため費用が高くなります。また、裁判で勝っても支払いがなく差し押さえになっても財産がなかった場合、弁護士費用や諸費用はもちろん回収できません。
民事調停
裁判所に間に入ってもらい、和解を目指します。現実的にいくらまでなら払えるのか、どのような支払いサイトにするのかを法的拘束力のある状態で債務者と同意をする法的手続きです。費用は債権額に応じた印紙代(数百円〜)のみで、弁護士にも必ずしも依頼する必要はありません。完全に取りっぱぐれるよりは、落とし所を探りたい場合には有効です。ただし、民事調停の日に債務者が現れなかった場合は無効になります。
個人顧客への債権回収を代行してもらうには
個人顧客への債権回収を代行してもらう場合、現実的には弁護士への依頼一択となります。債権回収会社も存在しますが、彼らが取り扱えるのは金融機関の貸付債権やリース債権等の特定金銭債権のみで、個人顧客に対する債権に該当するケースはほぼありません。
債権回収のノウハウを持っている弁護士に依頼すれば、そもそも回収できそうな債務者かアドバイスをもらえますし、督促から裁判、回収までの全てのフローを任せることができます。ただし、通常 数万円の着手金、成功報酬として回収金額の10〜30%が発生します。
個人顧客の未払いを防ぐには
個人顧客の未払いを防ぐのに一番確実なのは、決済機能のついたプラットフォーム経由で契約をすることです。そうすればそもそも事前に顧客が支払うケースが多いですし、後払いだったとしても未払いの場合のリスクはプラットフォーム側が負うことになります。
とはいえ、毎月の使用料や契約費用のコストが見合わない、自身が提供しているサービスに合うプラットフォームがない、直接取引をする業界慣習であるなど、様々な理由で直接取引となるケースもあるはずです。その場合は、事前に必ず契約書を交わす、キャンセル条件に同意してもらう、料金体系を理解してもらうなどを、書面でエビデンスを残しておきましょう。理解不足や低モラルによる未払いを防ぐことにつながります。
また、実際に未払いが発生してしまった場合は、継続してまめに連絡をとり続けることが大切です。放置をしてしまうと、ここは支払わなくても大丈夫そうと思われてしまい、回収まで長期化したり法的手段に出ることでコストが嵩むリスクがあります。
督促連絡は本記事で紹介した通り、SMS・メール、電話、書面で行いますが、未払いの顧客が一定数いる場合は督促業務に割くリソースは大きくなります。本来注力したいサービスに集中できない、業務負荷が増えて残業等が増えるといったデメリットも生じます。督促業務の自動化も検討すべきでしょう。
ソフトプラン株式会社ではオートコールシステム「発助」を提供しており、自動音声による督促電話にもご利用頂いております。

